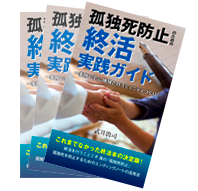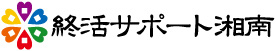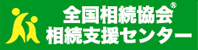■相続登記の義務化が相続手続全体に与える影響とは!
毎年のことですが、新年度を迎えると、新たな場所で慌ただしい日々を過ごす方も多いのではないかと思います。
相続に関しても新たな動きがありました。
2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。
義務化されたということは、当然の如く、それまで相続登記に関して義務がありませんでした。
義務がなかったがゆえに弊害がありました。
相続が発生していても不動産に関して、相続登記を行わなかったケースが多発しました。
これには、様々な理由がありますが、主な理由としては、
1.期限がない故、相続登記に関して、手を付けることなく放置してしまった
2.遺産分割で揉めて争いになってしまった
3.相続人の中に連絡を取ることができなかった者がいた
4.相続登記を行わないままでいたら、相続人が亡くなってしまい、相続関係が複雑になってしまった
他にも理由はあると思いますが、結果的に相続登記が行われないまま放置された状態になってしまいました。
その結果、所有者がわからない所有者不明の土地が全国で発生しました。
その面積は九州に匹敵します。
これでは、土地の売却ができず、再利用などが進まない状況になってしまいました。
所有者不明の土地問題は社会問題にまで発展してしまいました。
つまりは、相続登記に義務がないということは、政策的な誤りであったわけです。
そのような経緯を踏まえて、2021年(令和3年)に法律の改正が行われ、相続登記が義務化されるに至りました。
相続登記の義務化の内容は、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
3年という期限は、遺産分割で争いになったときのことを想定して、この期限になったのではないかと思います。
遺産分割協議がまとまった場合も遺産分割から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由もなく、3年以内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化は、相続手続全体に影響を与えるものとなりました。
相続登記が義務化されるという情報を知った相続人の方は、「相続登記が義務化されるので、登記が完了していない土地や建物の手続を進めてほしい」といった相談や依頼も増えています。
ちなみに相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に申告するという期限があります。
この期限があることによって、期限内に申告しなければならないという相続人の意識付けになります。
ただし、相続税の申告が必要なケースが対象ですから、申告が不要な場合は関係ありません。
ですから、相続登記の義務化により、相続税の申告と同様に相続人の意識付けに役立つのではないかと思われます。
その意味で相続登記の義務化は、相続手続全般に影響を与えることになります。
申請期限を意識して、不動産だけでなく、預貯金・有価証券・自動車等の財産に関しても各相続人が協力や妥協等を考慮してもらえれるのではないと思います。
そうなれば、今まで以上に円滑に相続登記が行われることと思います。
それでも、相続人の中には、わがままで自分勝手な人であったり、強欲な人も見受けられます。
遺産分割がまとまりそうもないときは、相続人申告登記という制度もできました。
これからの動きに注目していきます。